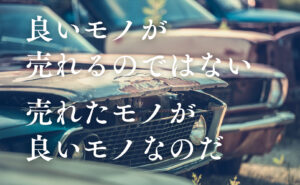バドミントンサークルを運営で利益を得ることに対し、モヤモヤした気持ちになる方は少なくないでしょう。もしあなたがそう思ってこの記事にたどり着いたのなら、ぜひ読んでみてください。あなたのモヤモヤが少しでも解消されることを願っています。
参加費から利益を得ることへの罪悪感
実はかつて筆者もばっちり感じていました。
サークルを始めたての筆者の場合はかなり重症で、利益を細かく記録して、参加比率に応じて返金していました。
それでも筆者は黒字に拘っていたのでまだ良い方ですが、罪悪感に負けて赤字で運営する方は大勢いらっしゃいます。
なぜ利益を得ることに罪悪感があるのでしょう
❶お金を稼ぐ=悪の文化
日本には、『お金を稼ぐ=悪い』という根強い文化があります。
こういった文化を紹介する記事は多く、一例として以下のリンクのブログ記事を紹介させていただきます。

アメリカではお金を稼ぐ人ほど民に尊敬され、社会貢献度の高い人だという認識が根付いています。
なんで日本には「お金を稼ぐことは悪い」という風潮が? (happytraveling555.com)
❷余剰金に対するメンバーの反応
集めた参加費の余剰金を公平に使わないと、文句を言うメンバーが出てくることがあります。
『文句を言うメンバー』と少しメンバーに非があるような書き方をしましたが、その方が『参加費に利益は含まれていない』と信じている場合があります。運営側が『参加費に利益は含まれていない』というスタンスでいることが原因となっているかもしれません。
 としかず
としかず「必要な金額しか頂きません」というコメントを信じて加入したのなら、文句が出てもしょうがないかな。。。
❸悪徳なサークルと混同されるのが怖い
健全にスポーツ活動を行っている団体に混ざって、大変残念ですが、様々な勧誘を行って不正に利益を得ようとする団体もいます。こういった団体と活動対価を得る団体が混同されるのを避けようとして無償にしてしまうのでしょう。



いやもう、利益とるの恐いわ
無償であっても「無償アピール」は控えめに
コミュニティ運営をされていて「無償で良い」と考えていることは、それぞれの考えがあって良いと思います。しかし「無償です!ボランティアです!という主張を行うこと」は、ご自身のために行っているはずの「ボランティア」の本質とは異なります。
もしそれを前面に押し出すのであれば「他人から承認を得たい」または「無償という言葉で人を集めたい」のどちらかの目的でしょう。
特に「他人からの承認を得たい」という考え方は少し危険です。


『ボランティアだから』という理由で指示に従わせる



こら!言うことを聞け!こっちはボランティアで、プライベートの時間を使って準備しているんだぞ!



すみませんでした!すぐにやります!
いつもありがとうございます!



もっと感謝されても良いくらいだぞ!ボランティアなんだからな!
ボランティアという言葉は、本来は暖かく、前向きな意味を持つものです。しかし、それを理由に他人を従わせると、逆に良くない雰囲気を生み出してしまいます。猫部長ほどではなくても、無意識のうちにメンバーに圧力をかけてしまうこともあります。
バドミントンサークルの運営者は利益を得た方が良い理由
❶お金は「人を喜ばせた対価」だから
ビジネス全般に言えるのですが、お金は「労働(どれだけ時間をかけたか)の対価」ではなく「困っている人や課題を解決し、人を幸せにした対価」なんです。コミュニティにおけるバドミントン活動の提供は、しっかりと大勢を喜ばせています!
❷バドミントンとコミュニティの価値を守るため
昨今、筆者はバドミントンが安売りされすぎていることを気にしています。なぜフットサルより安価で、バスケットボールと同じ水準なのでしょう。バドミントンは単位面積あたりに入れる人が僅かで、風のない場所が必要であり、どの球技より消耗する球を使うスポーツです。これらを考慮すると、安売りされるべきではありません。
加えて一般人にはなかなか実行できない「人を集めること」の価値も見直してください。もしこの価値が低ければ、みなさん個人で体育館に向かうだけで済んでいるでしょう。
私達が行っているバドミントン活動を行うコミュニティは非常に価値が高いものなのです。



自信を持ちましょうね!
❸チームが発展するから
金銭に余裕が生まれると、投資という選択肢が生まれ、アイデアも湧いてくるようになります。
- コーチを招待しよう!
- ノックマシンを買おう!
- チームウエアを作ろう!
- 良いシャトルを使おう!
上記は一例ですが、これらがサークルに付加価値を与え、継続性も高まりチームメイトは得をすることなります。運営者が多少でも利益を得てれば、双方が得をする状態になります。
そしてもっと広い視点から俯瞰してみると
バドミントン界全体の発展に貢献していることになります。
ここだけは注意しましょう
❶営利目的の体育館利用が禁止されている場合がある
体育館によっては、営利目的の利用はできなかったり、料金が割り増しになったります。利用前に必ずルールを確認し、守るようにしましょう。
これを避けるためにNPO(非営利団体)を設立するケースもあります。NPOは営利を目的としませんが、利益を上げることは可能な団体です。



参加費の徴収方法など工夫次第で回避できそうですが、、、きちんと確認しましょうね!
❷確定申告を忘れずに
本業とは別に、年間20万円以上の収益を得ると、確定申告をして所得税を支払う義務が生じます。
ただしバドつくでは、仮に収益を得ていなくても、確定申告をすることをお勧めします。
詳細は以下のリンク先で確認してください。おすすめの記事です。
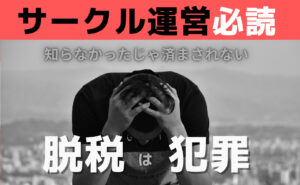
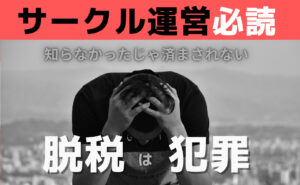
実際、そんなに稼げません。笑
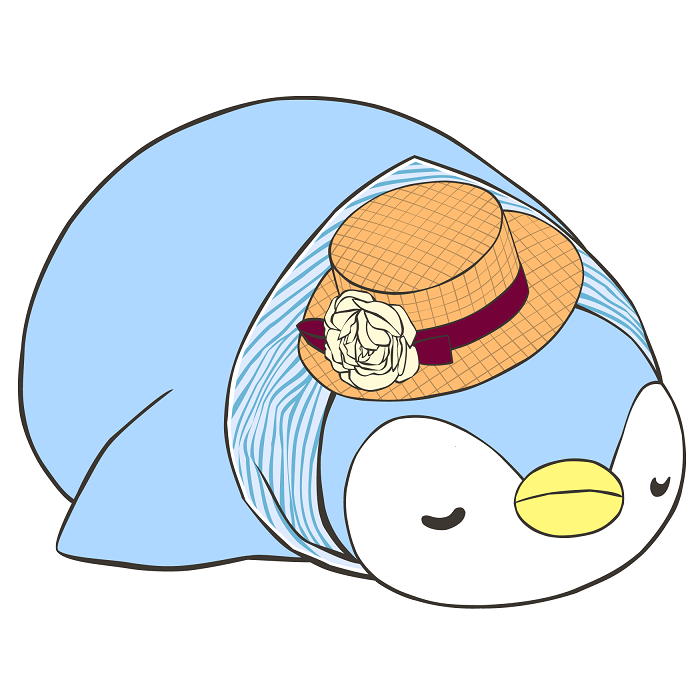
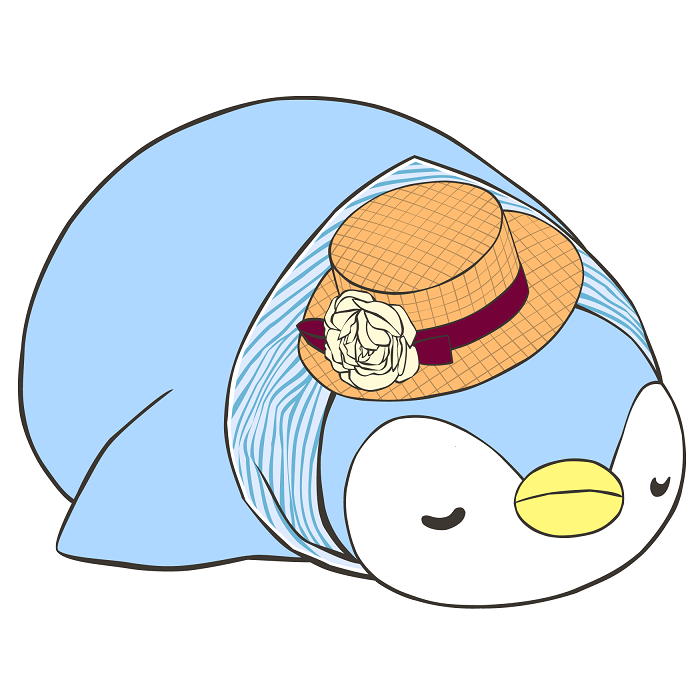
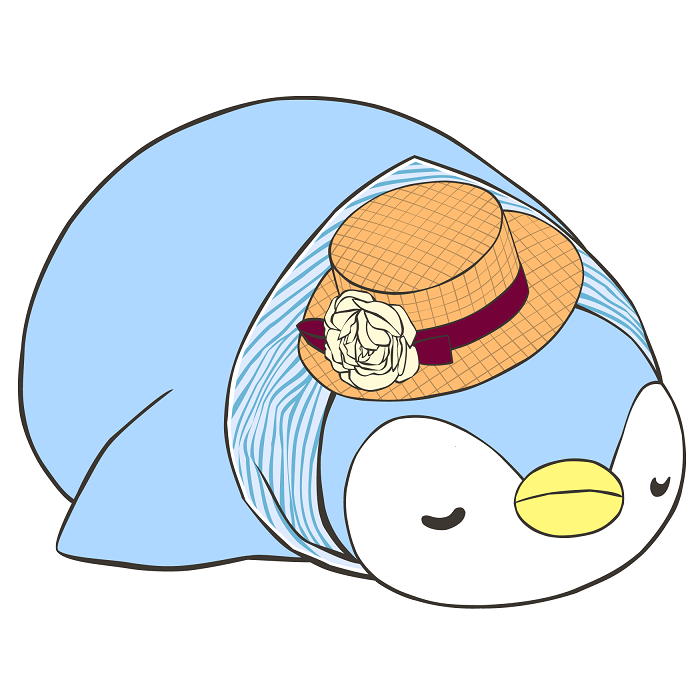
いや、前半稼げるテンションやったやないかーい!



あぶねーギリギリ黒字。。。
2023年損益(としかずのサークル)
売上:152.8万円
経費:152.7万円
利益:1,219円
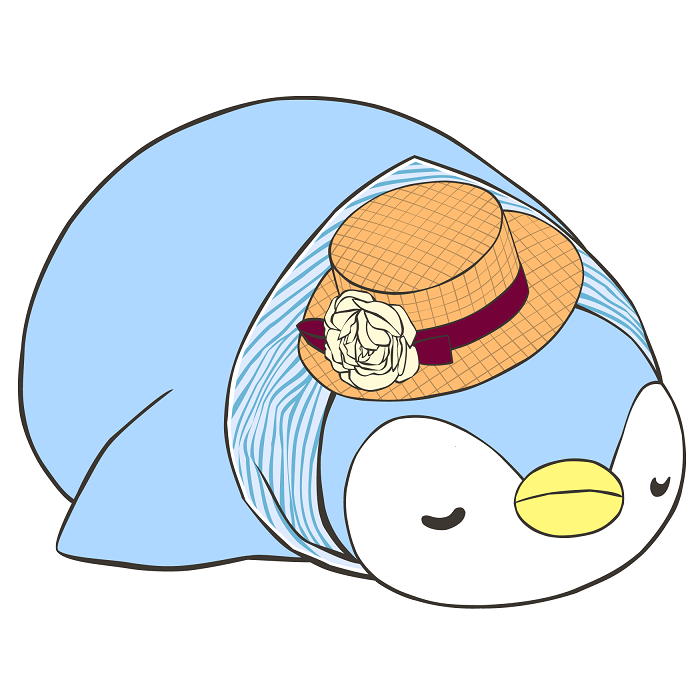
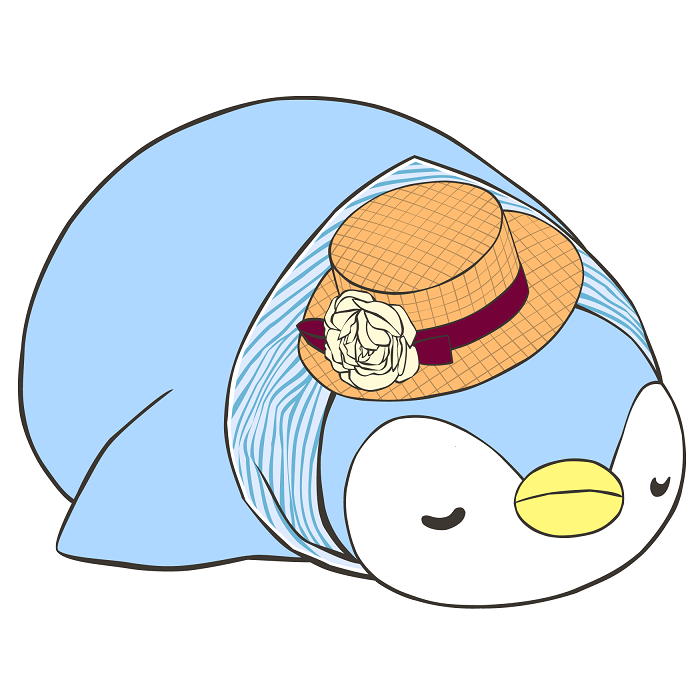
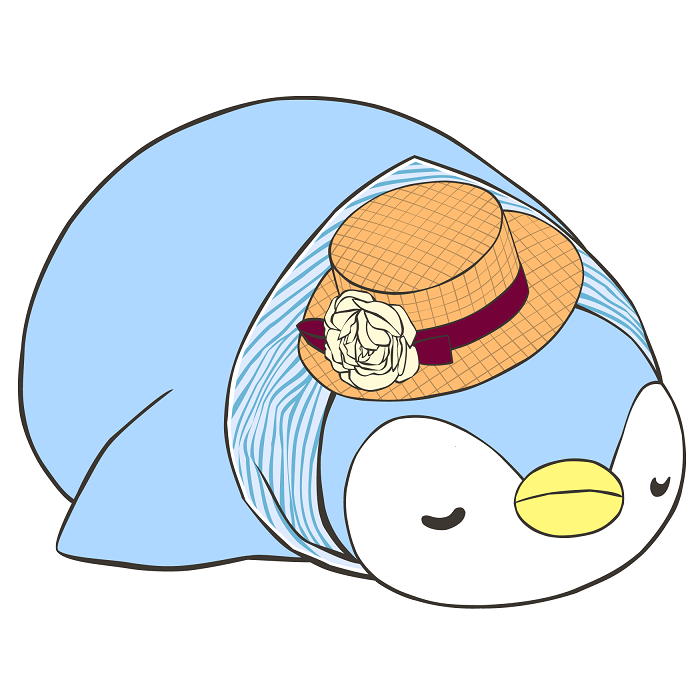
利益率ひっく!!経営下手くそやん!!
額が大きいからもうちょっと余裕がないと!



お金余ると色々経費でやっちゃうんだよねー
良い体育館も使いたくなっちゃう…
筆者は利益を得るアレルギーが取れているのですが、チームへの投資が楽しすぎて、結局筆者は、収益化に向いていないのでした💦
まとめ
運営者が自分の時間や労力をかけて、サークルを円滑に運営し、メンバーにとって有益な環境を提供するためには、適切な報酬を受け取ることは自然なことです。
逆に利益を受け取らないことで、不健全な状態に陥る可能性があり、低価格競争はバドミントンとコミュニティの価値を自ら下げるリスクが大きいです。
適切な収益を得ることで、サークルの長期的な発展が可能となり、メンバーにはより良い環境が提供できるでしょう。バドミントン界全体の発展にもつながります。
勇気がでない方も透明性を保ち運営者がどのようにサークルの資金を使っているかを明確に示し、メンバーの信頼を得ることで、健全なサークル運営をしていきましょう。